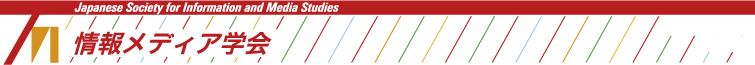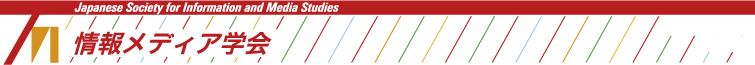第26回研究会を開催
2024年11月2日(土),大妻女子大学およびオンラインにて,第26回研究会を開催しました.今回の研究会は昨年に引き続き対面での発表会と,オンラインからの参加を同時に行うハイブリッド開催でした.
参加者はオフライン参加:24名,オンライン参加:1名参加者合計:25名でした.参加申込は30人を超えていましたが,当日は台風の影響で交通機関が乱れ参加できなくなった方がいらっしゃいました.時間に間に合わない発表者もいましたので,一部順番を変更させてもらいました.すべての発表が終了した後,聴衆による投票を実施した結果,植村八潮氏,野口武悟氏による「視覚障害者の電子書籍等ウェブコンテンツ利用のノウハウを可視化する試み」が最優秀発表賞に選ばれました.
今回の研究発表では,図書館情報資源をテーマにしたもの,学術情報の特性に関する分析がなど7題集まり,充実した研究会となりました.
当日の参加者に配布した発表要旨『第26回研究会発表資料』には若干の残部がございま
すので,ご希望される方は事務局にご連絡ください.請求書(500円+送料180円)を同封して郵送いたします.
■ 研究会開催概要
日時:2024年11月2日(土)13:00-17:20
会場:大妻女子大学 千代田キャンパス G棟525教室+オンライン(Zoom)
【 会員による一般発表 】
-
〇渡辺真希子(帝京大学共通教育センター)
情報メディアに関する費用体系の分析:人文科学系学生が利用する情報メディアを用いた予備分析
発表予稿 
-
〇片山ふみ(聖徳大学文学部),河内ひより(聖徳大学文学部),唐津日陽(聖徳大学文学部),秋葉桃子(聖徳大学文学部),木間礼子(聖徳大学文学部),髙嶋かなえ(聖徳大学文学部),髙山みのり(聖徳大学文学部),山中友紀子(聖徳大学文学部)
日本の公立図書館におけるBL図書の提供に対する人びとの意識 アンケート調査の中間分析
発表予稿 
-
〇植村八潮(専修大学文学部),野口武悟(専修大学文学部)
視覚障害者の電子書籍等ウェブコンテンツ利用のノウハウを可視化する試み
発表予稿 
-
〇小牧龍太(共立女子大学文芸学部)
モビリティーズの社会学としての「図書館情報資源概論」
発表予稿 
-
〇佐藤千晴(筑波大学大学院 人間総合科学学術院人間総合科学研究群 情報学学位プログラム),池内淳(筑波大学図書館情報メディア系)
情報検索能力と認知能力・認知判断傾向に関する分析
発表予稿 
-
〇小野寺夏生(科学技術・学術政策研究所)
標本サイズの増大に伴って形状が変わるLotka型確率分布関数の導出 "Success breeds success" (SBS)確率過程に基づく解
発表予稿 
-
〇中西陽子(日本大学医学部),五味悠一郎(日本大学理工学部)
がんの診断支援を目指すガイドラインの形態素解析による情報組織化
発表予稿 
■ 最優秀発表賞
-
植村八潮(専修大学文学部) 野口武悟(専修大学文学部)
「視覚障害者の電子書籍等ウェブコンテンツ利用のノウハウを可視化する試み」
■ 受賞者インタビュー
Q1. 受賞の感想をお聞かせ下さい
-
植村は、これまで賞とはまったく無縁な人生を送ってきましたが、これで履歴書や研究者プロフィールにどうどうと書くことができます。もちろん、光栄にもこのような素晴らしい賞をいただけたのは、共同研究者の野口武悟先生のお力に寄るところが大です。最優秀発表賞は、指導したゼミ学生が2名が、これまで受賞しています。いつか自分もほしいなと、狙っていたところもありますが、何よりも発表を聞いていたいた皆さんから評価をいただけたことを非常に光栄に思います。
Q2. 研究テーマの選定理由を教えてください
-
読書バリアフリー法の施行で視覚障害者等による電子書籍利用が注目されています。長年の研究テーマである電子書籍が、すべての人が読書できる社会の実現に大きく寄与できると思い、アクセシブル電子書籍を研究テーマにしました。視覚障害のある読者は、スクリーンリーダーや音声ガイドの助けを借りて、電子書籍を入手し、音声合成により“聞く”読書をすることになります。ところが、そのハードルはとても高く、誰でもが身につけられるスキルとは言い難く、また、スキルの獲得は個人の努力に負っています。視覚障害者等がICTスキルを高めるための指導方法やマニュアルも整っていないのです。第一段階としてとして、電子書籍の読書に慣れた視覚障害者がどのようにして読みたい本を探し、購入したのか、利用のノウハウをまとめられないかと考えました。
Q3. 発表の準備などで苦労した点や工夫した点を教えてください
-
研究発表では、どんな小さなことでも発見があり、聞いた人に驚きが伝わることが必要と思っています。“発見”はなにか、その面白さは何か、短い時間で適切に伝わるように心がけています。また、スライドでは、概念をなるべく図解して、直感的な理解の助けにしています。あと、今回は、共同研究者の野口先生がご都合で参加できなかったので、一人で発表になりました。元来、早口なのですが、一人だとなおさら早口になりがちなので、ゆっくり話すように心がけました。
Q4. 受賞を受けて、周囲の方々の反応はいかがでしたか
-
野口先生が、受賞についてFaceBookにすぐにあげていただいたので、“いいね”がいっぱいつきました。また、研究に協力いただいた視覚障害者の人たちにも喜んでいただきました。
Q5. 今後の目標などありましたらば、教えてください
-
発表でおわかりのように、研究は道半ばです。「ノウハウを可視化する試み」に留まっています。今後、研究を進め、視覚障害者が電子書籍を読むためのガイドブックやマニュアル、さらに指導方法を確立したいと思います。そこに向けて、また、情報メディア学会の場で発表しますので、ご指導のほどお願いいたします。